最終更新日:2022年1月29日
朝起きられない「起立性調節障害」…適切な治療と「学校に求められる対応」
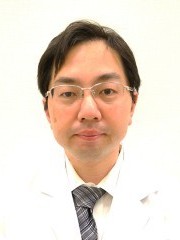
こちらの記事の監修医師
高座渋谷つばさクリニック
武井 智昭

朝起きられない、めまいがする…といった症状の頻発する学生は、もしかしたら「起立性調節障害」かもしれません。思春期によく見られますが、成人してからも改善されないケースもあります。れっきとした体の病気ですが、あまり理解されていないことで苦しんでいる患者も多いようです。高座渋谷つばさクリニックの武井智昭氏が解説していきます。
「決して怠けているわけではない」起立性調節障害という疾患
起立性調節障害は、自律神経機能の低下によって起こります。
視床下部など、脳の中枢神経が機能変化し、血流などがコントロールされることが原因です。
小学校高学年から中・高校生までの思春期に好発し、朝起きられない、長時間起立時にめまい・動悸・立ち眩みが生じるといった症状が見られ、悪化すると不登校につながることもあります。
原因疾患は明らかではありませんが、自律神経の乱れには、思春期における心身の発育によるものに加えて、睡眠不足、運動不足、精神的ストレスなど多岐にわたる理由が挙げられます。
また、本疾患は家族性に発生する可能性があるとされています。
決して怠けているわけではありません。この疾患に対して保護者・学校教諭が理解を深め、適切な治療・生活習慣の改善に取り組み、学業においては適切な配慮をすることが求められます。
ここでは、起立性調節障害と診断された方の「治療法」「生活を送る上での対処法」について解説していきます。
薬も使用するが、メインの治療は「非薬物療法」
治療は、日常生活での対応等の「非薬物療法」と「薬物療法」に大別されます。
多くの症例では薬物療法のみでは改善が見込めないため、日常生活の改善から取り組みます。
まずは「睡眠」生活リズムを改善
日常生活においては、まず、十分な睡眠をとることが重要です。
思春期になると、就寝時間が24時を過ぎ睡眠不足となる傾向にあるうえ、就寝前にスマートフォンやパソコンを利用し、脳がブルーライトによる刺激を受けていることが多いです。
就寝時間が遅い場合には、1週間に30分程度ずつ前倒ししていく、就寝前のパソコンやスマートフォンなどの利用を控えて自然睡眠を促すことも重要です。
また1日30分程度のウォーキングなどの運動も、筋力維持や、自然睡眠を促す観点から重要です。
朝は、ご両親がカーテンを開けて日光を部屋にとりこみ、声をかけることで、覚醒リズムを促すことが重要です。
そして頭を下げ、1-2分程度の時間をかけてゆっくりと起き上がるようにさせてください。
また朝礼などで、長時間起立していると血流は下半身にたまり、脳(頭)への血流が低下して、立ち眩み・めまいなどの症状が誘発される可能性があります。
こうした症状があればしゃがむ、足を動かす、クロスさせる、マッサージをするなどして筋肉を動かすことで血流を押し戻すのが効果的です。
「飲食」での改善も
循環する血液量を増やすため、1日あたり2~3リットルの多めの水分を努力して摂取してください。
塩分も、腎機能低下や高血圧がなければ10~12gと多めに摂取することもポイントです。
醤油やソースを多めにかける、ラーメンやうどんなどはスープまで飲む、漬物を1人分多く食べるなどすると、比較的簡単に摂れます。
学校への「通い方」
起立性調節障害は自律神経の疾患で、心身症の1つの状態であるため、心の状態変化の影響を受けやすいです。そのためストレスは症状悪化の大きな要因となります。
こうした症状が悪化して学校に行けなくなることもありますが、決して怠けているわけではありません。当事者であるお子さんはつらく感じているはずです。
まずはご家族の方が「学校へ行けない焦り」などの苦痛を理解し、頑張っていることへ共感の態度を示すことが重要です。
朝から終業まで学校へ行くというのはハードルが高いので、「3時間目から登校する」など低くして、心理的負担を軽減するのもよいでしょう。
この疾患は昼から夕方にはエンジンがかかったように症状が軽減する傾向があります。
学校側に疾病の理解を深めてもらうには、受診した医療機関から診断書(診断名および重症度、学業上の具体的な配慮を記載したもの)を提出することが効果的です。
「薬物療法」使用される薬は…
薬物治療としては、血圧低下や頻脈に対して循環状態を改善させる「昇圧剤」が投与される場合があります。
また、抑うつ傾向があれば抗うつ薬、睡眠確保が困難であれば睡眠導入薬、めまい等に対しては漢方薬など、症状にあわせた様々な対応が実施されますが、必要最低限の処方で、中長期的には改善していくことが多いです。
軽症であれば半年程度での改善が見込まれますが、不登校が持続する中等症・重症の例では数年単位の長い治療期間を要する場合もあります。
成人しても「起立性調節障害」が続くワケ
思春期が終わる18歳(高校3年生)のころには症状が軽減する傾向にありますが、重症度が高い場合、成人となっても自律神経のバランスを崩しやすい体質が残るため、症状が持続したり、あるいはストレスにより再発したりすることも十分にありえます。
成人となると、生活リズムの乱れや不規則勤務、飲酒などが契機となるため、症状が悪化するレベル(キャパシティ)を把握した上で、自己管理が重要となっていきます。
「怠けている」ワケではない…「周囲の理解」が重要課題
この疾患を理解していない方からは、「怠けている、さぼっている、性格がおかしい、精神疾患だ」と勘違いされることも多いです。そうした偏見から精神的に負担がかかることで、症状が悪化した例の診療もおこなってきました。
この疾患は、本人の意思が関わるものではありません。「疾患の特性を周囲の人へ話す機会を設ける」「環境を調整する」といった協力が、症状改善には重要であると、再度強調しておきます。
0歳から100歳まで「1世紀を診療する医師」
この症状を治したい。記事を読んで今すぐ医師の診断を受けたいあなたへ。
イシャチョクのオンライン診療なら、予約なしで今すぐ医師とつながります。「オンライン診療について詳しく知る」ボタンから、オンライン上の仮想待合室に入りましょう。全国の医師、または近くの医師が、すぐにあなたを診察します。
全国のクリニックから検索したいあなたへ。
クリニックを探すクリニック検索
病気・医療情報検索
キーワード検索キーワード検索
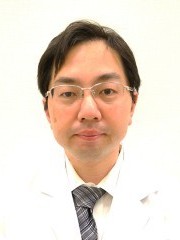
こちらの記事の監修医師
高座渋谷つばさクリニック
武井 智昭
小児科医・内科医・アレルギー科医 2002年、慶応義塾大学医学部卒業。多くの病院・クリニックで小児科医・内科としての経験を積み、現在は高座渋谷つばさクリニック院長を務める。
感染症・アレルギー疾患、呼吸器疾患、予防医学などを得意とし、0歳から100歳まで「1世紀を診療する医師」として地域医療に貢献している。
仮想待合室型オンライン診療対応の医療機関募集中
イシャチョクでは、予約無しでオンライン上の「仮想待合室」に入れば、診療科目毎の医師が順番に診察してくれる、仮想待合室型のオンライン診療システムを提供しています。以下のボタンをクリックして、オンライン診療に対応しているクリニックを検索してみてください。
-
- 神奈川県大和市渋谷5-22地図を見る
- 046-279-5111
- 内科 小児科 アレルギー科
高座渋谷つばさクリニックは、小田急電鉄江ノ島線「高座渋谷駅」より徒歩すぐにあります。内科・小児科・アレルギー科の診療を行っています。地域の健康を守るプライマリケア医師が常勤しており、少しでも不安に思っ...
- 09:00 - 12:00
- 14:00 - 18:30
- 月
- ●
- ●
- 火
- -
- -
- 水
- ●
- ●
- 木
- ●
- ●
- 金
- ●
- ●
- 土
- ●
- -
- 日
- -
- -
- 祝
- -
- -
※休診日:火曜・土曜午後・日曜・祝日
※受付時間は、診療開始時間から診療終了時間30分前迄です。※健康診断・予防接種はコロナ禍に限り
11:00~12:00 , 14:00~15:00
にて承ります。(要予約)









