最終更新日:2023年3月1日
幼い子どもの10人に1人が経験する「熱性けいれん」とは? いざという時慌てないための正しい知識と対応
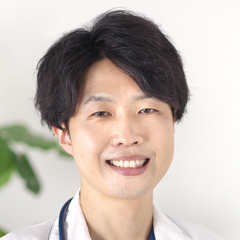
こちらの記事の監修医師
岩手県立磐井病院
金森 啓太

子どもが発熱時、けいれんなどを起こしてしまう「熱性けいれん」。親御さんが正しい知識や対応法を身につけていれば、いざという時に慌てることなく対処できます。2023年に8年ぶりに改訂されたガイドラインの内容を踏まえ、けいれん、てんかん、発達遅滞、神経発達症(発達障害)などの小児神経科を専門とする小児科医が解説します。
目次
「熱性けいれん」とは? ガイドライン2023を踏まえ解説
8年ぶりのガイドライン改定。何が変わった?
熱性けいれんとは?-原因や症状
熱性けいれん以外の病気
熱性けいれんの分類-「単純型」と「複雑型」
熱性けいれんの再発率
熱性けいれんと「てんかん」発症率の相関
熱性けいれんは遺伝する?
子どもの「熱性けいれん」で慌てないために……予防薬や正しい対応方法などの知っておきたいこと
熱性けいれんが起きた時、すぐにするべき対応
1.冷静に安全を確保
2.体を横に向ける
3.けいれんの様子をよく観察する
けいれんが続くなら……救急車を呼ぶ目安は「5分」
すぐに治っても病院は受診したほうがいい?
自宅で使える薬はある? 予防薬・治療薬について
ダイアップ® (ジアゼパム坐剤)
使い方
ブコラム® (ミダゾラム口腔用液)
使い方
ダイアップ®・ブコラム®の注意点
終わりに
「熱性けいれん」とは? ガイドライン2023を踏まえ解説
熱性けいれん(熱性発作)は、発熱に伴いけいれん(発作)を起こす疾患です。
日本で熱性けいれんを起こす人は、多く見積もると9%であり、およそ10人に1人は熱性けいれんを経験します。たとえば30人のクラスがあるとすると、2~3人は熱性けいれんを経験していることになります。熱性けいれんはそれだけ身近な疾患です。
一方で、我が子がけいれんを起こしたときに、自信を持って正しく対応できるという親御さんは少ないと思います。医療機関を受診して説明を受けた後でも、心配事も多いと思います。
8年ぶりのガイドライン改定。何が変わった?
熱性けいれんは2023年に診療ガイドラインが改定されました[1]。
全体の構成は大きく変更されておりませんが、
・遺伝に関する項目
・発熱時の予防薬「ダイアップ®」に関する情報
・「熱性けいれん」→「熱性けいれん(熱性発作)」への表記変更
これらの内容が更新されました。この変更を踏まえ、最新の情報をもとに解説いたします。
熱性けいれんの症状は、「けいれん(手足を突っ張らせたり、ガクガクさせたりする)」だけではなく、「ぼーっとする」、「力が抜ける」、「一点を見つめ視線が合わなくなる」などの様々な症状があります。これらをひっくるめて「発作」、もしくは「てんかん発作」といいます。
新しいガイドラインでは、「熱性けいれん」→「熱性けいれん(熱性発作)」という表記に変わっています。
以下の文中では、わかりやすさを重視して「熱性けいれん」や「けいれん」と記載しますが、このような「けいれんとは違った症状」もあることにご注意ください。
熱性けいれんとは?-原因や症状

生後6か月~5歳くらいの子どもで、発熱に伴ってけいれんを起こす病気です。
子どもは脳の神経が成熟していないため、急な体温上昇に対応できずに、脳が過剰に興奮してしまい、けいれんすることがあります。
熱があってけいれんを起こす病気は、熱性けいれんの他にもいくつもあり、中には怖い病気もあります。熱性けいれんと診断するには、熱性けいれん以外の病気を否定することも重要であり、医師の判断が必要です。
熱性けいれん以外の病気
「発熱+けいれん」の症状があるもので、熱性けいれん以外にはどのような病気があるかを紹介します。
脳(中枢神経)の感染症として、髄膜炎や急性脳炎・脳症があります。また、けいれんを繰り返す脳の病気である、てんかんの可能性もあります。他には、頻度は少ないですが、電解質異常や低血糖、代謝異常、頭蓋内出血などでけいれんを起こしている可能性もあります。
これらの病気は、対応や予後が熱性けいれんとは異なるため、診察所見や経過から疑った時は、血液検査や髄液検査、画像検査などの検査を行うことがあります。
熱性けいれんの分類-「単純型」と「複雑型」
熱性けいれんは、「単純型熱性けいれん」と「複雑型熱性けいれん」に分けられます。
以下の項目のいずれかに当てはまる=複雑型熱性けいれん
・左右差のあるけいれん、身体の一部分だけのけいれん(焦点発作)
・1回の発熱で2回以上のけいれん
・けいれんの持続時間が15分以上
上記が一つも当てはまらない=単純型熱性けいれん
「複雑型だから治療が必要」とか「複雑型だから後遺症を残す」というものではありませんが、複雑型の場合は、熱性けいれん以外の怖い病気の可能性をいっそう警戒して、慎重に経過を診る必要があります。
複雑型熱性けいれんの場合、単純型熱性けいれんに比べて、将来のてんかん発症のリスクが高くなることがわかっています。しかし、複雑型熱性けいれんでも、大多数はてんかんを発症しません。
熱性けいれんの再発率
熱性けいれんの再発率は30~40%程度で、15%程度の子どもは3回以上繰り返します[2, 3]。つまり、熱性けいれんを起こした子どもの半分以上は生涯で1回だけですが、2回3回と繰り返す子どももいます。
以下の再発予測因子に一つも当てはまるものがない場合は、再発率は15%程度に下がります。
・両親やきょうだいに熱性けいれんを起こした方がいる。
・熱性けいれんを起こした年齢が1歳未満。
・熱が出てから1時間以内にけいれんを起こした。
・39度以下の熱でけいれんを起こした。
熱性けいれんと「てんかん」発症率の相関
熱性けいれんを起こしたお子さんが、将来てんかんを発症する確率は2.0~7.5%程度です。一般的なてんかん発症率は0.5~1%なので、それと比べると、てんかんの発症率が高いと言えます。ただし、90%以上はてんかんを発症しないため、過度に心配しすぎないことが重要です。
なお、熱性けいれんを起こした子どもで、以下の要素がある場合、てんかんの発症率が上がることが分かっています。
・発達や神経の異常がある。
・両親やきょうだいにてんかんの方がいる。
・複雑型熱性けいれん(上述)を起こした。
・熱が出てから1時間以内にけいれんを起こした。
・3歳以降に熱性けいれんを発症した。
熱性けいれんは遺伝する?
熱性けいれんは国によって有病率に差があり、そこには遺伝学的な理由があると考えられています。両親やきょうだいに熱性けいれんを経験した方がいると、熱性けいれんの発症率は高まることがわかっています。
どのくらい発症率があがるかは、まだはっきりとはしておりません。 オランダの報告では、熱性けいれんを起こした子どもの6.9%に両親かきょうだいの熱性けいれんの経験者がいたと報告しています[4]。
国によって違いが大きい病気のため、そのまま日本にも当てはまるものではありませんが、少なくとも「熱性けいれんの両親から生まれた子どもは、必ず熱性けいれんを発症する」というようなものではありません。そのため、正しい知識を身につけておくのは良いことですが、過度に心配する必要はありません。
子どもの「熱性けいれん」で慌てないために……予防薬や正しい対応方法などの知っておきたいこと
熱性けいれんが起きた時、すぐにするべき対応
1.冷静に安全を確保
まずは慌てず冷静に。お子さんを安全な場所に移動させてください。
周りに倒れてくるものはないですか? お子さんが転落する危険はないですか?
二次的な事故に遭わないように、安全な場所に移動させてあげましょう。
2.体を横に向ける
お子さんの体を横向きにしましょう。
嘔吐をすることがあります。あおむけにしていると、吐いたものが空気の通り道に入って、窒息する恐れがあります。吐いたものが外に流れ出るように横向きにしてあげるのがよいでしょう。
3.けいれんの様子をよく観察する
けいれんの様子をよく観察しましょう。
必須ではありませんが、可能ならば持続時間や様子をよく観察し、医師に説明できるようにしておいてください。スマートフォンなどで動画を撮るのも良いでしょう。
けいれんが続くなら……救急車を呼ぶ目安は「5分」

けいれんが5分以上続く場合は救急車を呼びましょう。
通常は5分以内にけいれんが止まり、意識も普段通りに戻ることが多いです。その場合は慌てて受診する必要はありません。落ち着いて病院を受診してください。
5分以上止まらない場合や、意識が普段通りではない場合は救急車を呼んで受診してください。5分以上けいれんが続く場合は、自然に待っていても止まらない可能性が高くなり、その場合は病院で薬を使って止める必要があります。
もちろん、「5分経っていないと救急車を呼んではいけない」なんてことはありません。
私個人の見解としては、「心配な時は迷わず救急車を呼んでいただいてよい」と考えています。
すぐに治っても病院は受診したほうがいい?
5分以内にけいれんが止まった場合でも、日中で気軽に小児科を受診できるのであれば、一度診てもらうことをお勧めします。
夜間でなかなか病院に行くのが大変な場合は、けいれんが止まっていて、受け答えや意識の様子が普段通りであれば、引き続き慎重に自宅で様子を見てもらい、翌日に受診をするので良いと思います。 しかし、ぐったりしている、元気がない、普段と様子が違うなど、なにか異変があったり、不安に感じることがあれば、その時点で夜間でも受診してもらった方が安心です。
自宅で使える薬はある? 予防薬・治療薬について
今後も熱性けいれんを繰り返すと予想される子どもに、予防するための坐薬(座薬)を出すことがあります。また、けいれんを止める薬も最近日本で使えるようになりました。

ダイアップ® (ジアゼパム坐剤)
ダイアップ®は坐薬(座薬)です。あくまでも予防の薬であり、けいれんを止めるための薬ではありません。けいれんが起きてから使うのではなく、熱がある度に坐薬 を入れることになります。次の項目で一般的な使い方について解説しますが、使い方はかかりつけの先生の指示に従ってください。
使い方
一般的には、発熱に気づいたときに1回目の投与を行い、最初の投与から8時間後も発熱があれば2回目の投与をします。注意点として、ダイアップ®を使用しても完全にはけいれんを予防できません。また、眠気やふらつきといった副作用が出るため、使用後は注意深くお子さんの様子を見守ることをお願いします。

ブコラム® (ミダゾラム口腔用液)
けいれんを止める作用を持つブコラム®という薬も、最近日本で使えるようになりました。シリンジ型の薬で、口の中(歯ぐきと頬の間)に注入します。
ダイアップ®は「今後も熱性けいれんを繰り返す可能性が高いと判断される場合」、ブコラム®は「長く続くけいれんが起きる可能性が高いと判断される場合」に処方されます。次の項目で一般的な使い方について解説しますが、使い方はかかりつけの先生の指示に従ってください。
使い方
一般的には、けいれんが5分以上続いて止まらない場合に投与します。シリンジ型になっており、口の中(歯ぐきと頬の間)に全量を注入します。ブコラム®を使用してもけいれんが止まらない場合や、呼吸が浅くなるなどの副作用が出る場合は速やかに救急車を呼ぶことが推奨されていますが、私個人の見解としては、ブコラム®を使用する場合は毎回救急車を呼んでよいと考えています。なお、年齢によって処方される量が変わりますので、処方されているものがお子さんの年齢に合っているか確認してください。
ダイアップ®・ブコラム®の注意点
ダイアップ®もブコラム®も副作用がないわけではなく、間違った使い方をすると危険な薬です。そのため、薬の必要性は医師が慎重に判断します。けいれんを繰り返す可能性が高いお子さんでも、持病によっては副作用のリスクの方が勝ると判断して出さないこともあります。
終わりに
熱性けいれんの事前知識がある親御さんと、熱性けいれんについて知らなかった親御さんとを比較した研究もあり、
事前知識がない親御さんでは、
・熱性けいれんは有害な病気だと思っていた
・熱性けいれんがありふれた病気であることを知らなかった
・命の危険や重篤な状態を連想した
という感想が多く、パニックになって適切な対応ができなかった割合も高くなりました[5]。
正しい知識を身につけ、なるべく焦らず正しく対応できるよう、この記事が役に立つと幸いです。
参考文献
- 日本小児神経学会(監), 熱性けいれん診療ガイドライン改定ワーキンググループ(編): 熱性けいれん(熱性発作)診療ガイドライン2023, 診断と治療社, 2023
- Pavlidou E, et al: Which factors determine febrile seizure recurrence? A prospective study. Brain Dev 2008; 30: 7-13.
- Offringa M, et al: Prophylactic drug management for febrile seizures in children. Cochrane Database Syst Rev 2012; 4: CD003031.
- van Esch A, et al: Prediction of febrile seizures in siblings: a practical approach. Eur J Pediatr 1998; 157: 340-4.
- Kanemura H, et al: Parental thoughts and actions regarding their child’s first febrile seizure. Pediatr Int 2013; 55: 315-9.
この症状を治したい。記事を読んで今すぐ医師の診断を受けたいあなたへ。
イシャチョクのオンライン診療なら、予約なしで今すぐ医師とつながります。「オンライン診療について詳しく知る」ボタンから、オンライン上の仮想待合室に入りましょう。全国の医師、または近くの医師が、すぐにあなたを診察します。
全国のクリニックから検索したいあなたへ。
クリニックを探すクリニック検索
病気・医療情報検索
キーワード検索キーワード検索
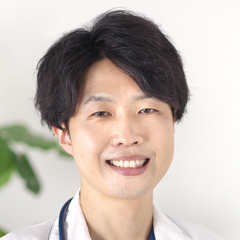
こちらの記事の監修医師
岩手県立磐井病院
金森 啓太
小児科医師
国立成育医療研究センター、東京都立小児総合医療センターで小児科、小児神経内科について研鑽を積み、地元の岩手県の医療に貢献するべく2022年4月から岩手県立磐井病院へ就職した。
専門は小児科、小児神経内科であり、特にけいれん、てんかん、発達遅滞(発達の遅れ)、頭痛などの疾患を得意とする。日本小児科学会専門医、日本小児神経学会員、日本てんかん学会員、日本頭痛学会員である。BLS(一次救命措置)、PALS(小児二次救命措置)のインストラクター資格を有する。













